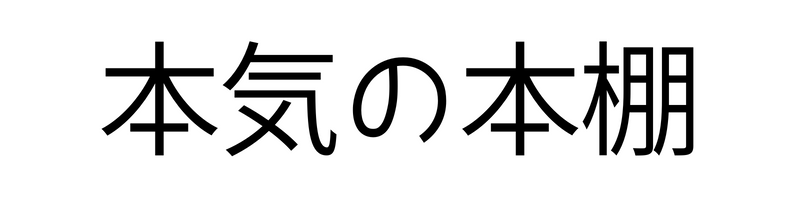まるで鏡だと思った。
なぜなら『夢見通りの人々』に登場する人物たちの姿には、自分という人間が映っている様に感じたからだ。
自分の持つコンプレックスだったり、弱さだったり、自分でも捉えきれない複雑な感情の動きだったり。
彼らの姿を自分と重ね見て、自分という人間の姿をありありと見た気分になった。
そしてこれまで以上に自分という人間を知った。
今回紹介する宮本 輝著『夢見通りの人々』には、自分を映す鏡となるような”生”の人間たちが生きている。その姿にどんな自分が映るかは人それぞれ違う。でも誰もが自分という人間を見つめることになる小説だと思った。
「夢見通りの人々」の内容紹介
『夢見通りの人々』は全十篇の連作短編小説。
そのため各話の登場人物と舞台は共通している。
物語で描かれているのは”夢見通り商店街に住む人々”についてだ。
この商店街に住む人々は本文の言葉を借りて言えば、”夢見通り”なんて名称にふさわしくないような人間ばかりが揃っている。
〈競馬狂いで夫婦喧嘩の絶えない太桜軒のおやじ。〉
〈ライオンズクラブのメンバーになりたくて PTA の会長、ゆめみ通り商店会組合長、少年野球チーム世話人、老人福祉会会長などの肩書きをすべて名刺に刷り込んでいる夢見会館というパチンコ屋の経営者。〉
〈金儲けが人生の全てであるかのように、店に入ってきた客に必ず何かを買わせずにはおけない村田時計店の、揃って一種偏執的な目つきをした夫婦。〉
他にも若い美男子しか雇わないスナックのママや、性欲を持て余している元ヤクザの肉屋の兄弟などがいて、挙げればキリがない。
個性派ぞろいの彼らだが、誰もに共通しているのは欠点ともいえる性質を抱えていることだ。そしてそれはコントロールできないから、人生は思いもよらない方向に向かっていく。
彼らが織り成す物語は、生きる人間の人生そのもの。読めば生きる喜びや哀しさ、複雑さ、可笑しさを実感できる。
緻密に表現された心の動き(ネタバレ含む)
本書の魅力の一つは複雑な心の動きが巧みに描かれているところだ。
だから登場人物の気持ちと行動が微妙に一致していないのに、妙に納得してしまうことになる。
たとえば作中に登場する光子の恋心がそうだ。
美容師の免許を取るために田舎から大阪にやってきた光子は、夢見通りでも悪名高い元ヤクザの竜一という男に好意を持つ。竜一は昔こそ刑務所に入るほどのワルだったが、今では更生して親の肉屋を手伝って暮らしている。全然タイプの違う二人だが、ある出来事をキッカケに親交を深めていく。
しかし光子は竜一の背中から肘に彫り込まれた刺青を受け入れられない。それで刺青を取ってくれれば結婚してもいいと光子は竜一に言う。
でもそこまで言っておいて光子は街を黙って出ていってしまいます。自分みたいな平凡な人間には竜一のような過去を持つ人間と一緒になることは重荷だと、誰にも何も言わず郷里に帰ってしまうのです。
あんまりだと思いませんか。
たしかに「女心と秋の空」ということわざがあるけど、ちょっと釈然としませんよね。
でもその一方で光子の気持ちが何となくわかる気もします。これまで平穏に暮らしていた人間にとって、竜一のような人間の登場は相当イレギュラーで自分自身戸惑ったはずだ。
それを考えればそんな結末にも納得してしまう気持ちになってくる。
こんな風に心情の微妙な動きにはリアリティがある。だから物語の中の登場人物が一人の意志ある人間のように感じてしまう。
それは見ごたえがあって、彼らの人生から目が離せなくなってしまいます。
おおらかな時代の空気感
本書の刊行が昭和61年(1986年)ということもあり、物語には古き良き時代の雰囲気が反映されている。
現代に比べて自由というか、おおらかさを感じるのだ。
中華屋の夫婦ケンカのシーンは、特に時代を感じた。
夢見通りの住人の一人である里美春太が客として中華屋に入ると、その店の亭主と奥さんが争っている。
亭主が浮気したと、奥さんがカンカンだ。
その争いは口ゲンカで留まらず、テーブルはひっくり返えるし、亭主は頭から血を流すし、奥さんは投げられて宙を舞うしのひっちゃかめっちゃかの大ゲンカに発展する。
でもそんな状況にもかかわらず春太がとりあえず注文してみると、二人とも何事もなかったように仕事に戻ります。
そのあっけからんとした態度が面白くて、その情景が頭に浮かんで笑ってしまいました。
今の時代、いかなる暴力も許せないという風潮があると思う。だからこんな夫婦ゲンカは下手すれば警察沙汰になってもおかしくないはずだ。
でもこの物語ではそれが許されるような雰囲気があって深刻にならない。大雑把で粗暴なんだけど、今の時代にはない寛容さがある。
その今にはない空気感を味わえるのも、この小説の面白さだと思った。
心根の優しい青年に会いに行く
僕は本書を何度も読み返している。
それは里美春太にまた会いたいという気持ちが、一つの動機になっている。
宮本輝作品に共通して言えることなのだが、物語には魅力的な人間が多く登場する。
本作の主要人物である里美春太もその一人だ。
春太は一見パッとしない青年だ。
女にはモテない。詩作に耽るが才能の芽は出そうにない。仕事は通信教育の営業をやっているがセールスがうまいわけでもない。当の本人も自分のことを冒険心に欠けてつまらない人間だと卑下する。
でも春太は周りの人間を安心させる人柄の良さを持っている。
だから老若男女を問わず商店街の人々は春太に悩みを相談するし、こじれた人間関係を取り持ってほしいと頼んだりもする。春太の持つ温厚な性格と近寄りやすい雰囲気の前に誰もが無防備になってしまうのだ。
そんな春太に、僕は憧れている。自分に関わった人が安らげるような存在に僕もなりたいといつも思ってしまう。
そして友人に会いに行くような感覚で、春太の優しさに触れたくてこの本を何度も手に取ってしまうのだ。
最後に
『夢見通りの人々』には脇役が登場しない。
登場人物の全員に積み重ねた過去があって、今を悩みながらも強く生きている。
それは当然現実の世界でも同じだ。誰にでも歩んできた人生があって、生活があって、家族がいたり恋人がいたり友達がいたりする。
でも普段はそんなこと意識しないから、他人をないがしろにしてしまうことがあると思う。
それは自分がしてしまうこともあるし、されることもあるはずだ。
そんな時、僕は作中に登場する「げえやん」と呼ばれる中年男の口癖を思い出す。
「いつまでも人をなめとったら、えらいめにあうで」
まさにその通りだ。